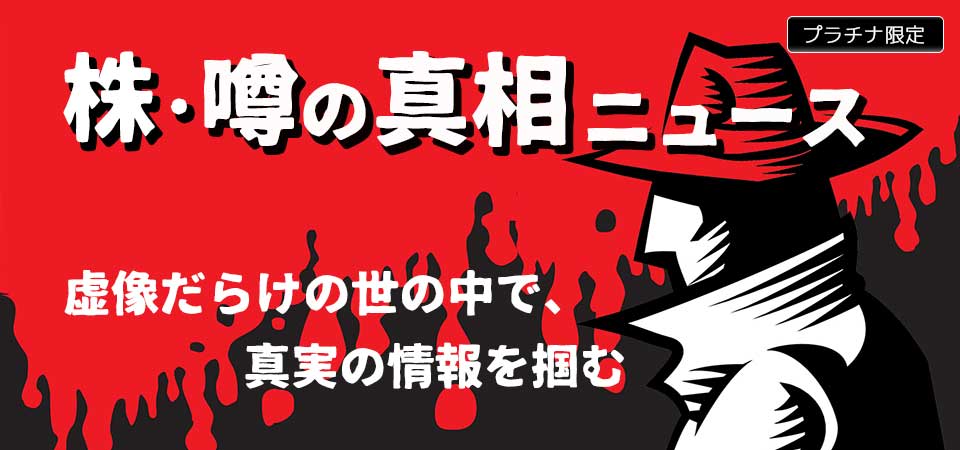石破茂という最悪カードを引き寄せた自民党議員
9月27日に投開票された自民党総裁選は、石破茂が決選投票で高市早苗を逆転して自民党総裁となり、10月1日に召集される特別国会の首班指名を経て第102代内閣総理大臣に就任してしまう。高市早苗については、世間では「ほとんど唯一」まともな政策を掲げるため待望論が盛り上がり、自民党員投票でも「主流派でないため政権への批判票が集まりやすいだけの」石破茂をわずかに上回っていたが、最後の最後でかなりの自民党議員が「世間感覚からかけ離れた(世論に背を向けた)損得勘定」で石破茂という日本国民にとって最悪カードを引き寄せてしまった。
すでに得票数が確定していた自民党員票を除いた議員票だけに注目すると、第一回投票ではトップが小泉新次郎の75票、以下、高市早苗が72票(一回目から麻生派の票が入っていた)、石破茂が46票、小林鷹之が41票、林芳正が38票、茂木敏充が34票、上川陽子が23票、河野太郎が22票、加藤信勝が16票だった。
決選投票では石破が第一回の46票から143票増の189票、高市が第一回の72票から101増の173票となり、自民党員票(決戦投票では各都道府県で1票)を加えて石破が215票、高市が194票となり、石破の逆転となった。
決選投票で石破に流れた議員票の143票は、小泉の75票、林の37票、河野の22票が確実で、茂木の34票、上川の22票の一部と思われる。これらの自民党議員は「世間からかけ離れた(世論に背を向けた)損得勘定」で、これから人事面等で論功行賞にありつくことになる。・・・・・・・・
この続きを読むには有料会員登録が必要になります。